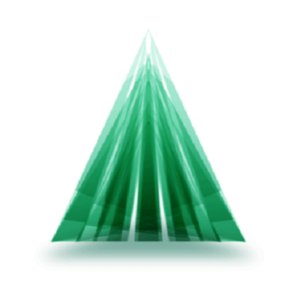読み物:血液がんにおけるcfDNAについて: マーク・ムラカミ博士とのQ&A
ムラカミ博士がプレシジョン・メディシンの追求を可能にする分子ツールについて語ります。

がん生物学の進歩と分子技術の革新により、プレシジョン・メディシン(精密医療)の分野が大きく変わりつつあります。次世代シーケンシング(NGS)をはじめとする先進的なツールの導入により、従来の画一的な治療から脱却し、患者一人ひとりの腫瘍の分子的特徴に合わせた個別化治療が可能になってきています。
ハーバード大学医学部助教であり、ダナファーバーがん研究所の血液腫瘍部門で独立研究者として活動しているマーク・ムラカミ医師にとって、この取り組みは非常に個人的な意味を持ちます。
「私が治療に関わってきた患者さんたちが、私の原動力です」と彼は語ります。「臨床研究やトランスレーショナルリサーチ(橋渡し研究)に携わる多くの研究者にとって、患者さんの存在こそが最大のモチベーションなのです。」
このインタビューでは、ムラカミ医師が取り組む血液がんの研究、リキッドバイオプシーの可能性、そしてセルフリーDNAの研究がどのように個別化医療の実現につながるかについて語っています。
Dr. Mark Murakami
マーク・ムラカミ医師は、ハーバード大学医学部の内科学助教授であり、ダナファーバーがん研究所の血液腫瘍部門において独立研究者として活動しています。血液がんの患者治療に加え、精密診断や個別化治療の発展を目指す研究室を主宰しています。その取り組みの中核をなすのが、分子診断技術です。
ムラカミ研究室の詳細については、こちらをご覧ください。

研究室の主な研究テーマは何ですか?また、どのようにして臨床上の課題に取り組んでいますか?
私たちの研究室では、血液悪性腫瘍を深く解析することに重点を置いており、特に治療中にもかかわらず腫瘍が持続する理由の解明に関心を持っています。私たちが主に研究しているリンパ腫は比較的進行の遅いタイプで、濾胞性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫、辺縁帯リンパ腫などが含まれます。
こうしたタイプのがんでは、多くの患者さんが最初の治療に良好に反応し、代謝的寛解(PETスキャンで陰性になる状態)に至ることが多いです。治療サイクルを3回〜6回行うと、画像上でがんが見えなくなるケースがほとんどです。しかしながら、一部の患者さんでは、早期に再発したり、より悪性度の高い形態に変化することがあり、これを事前に見極めるのが非常に困難です。
私たちは、病勢が持続するリスクのある患者を事前に特定できるようになることが、臨床的に非常に重要だと考えています。なぜなら、そうした患者は標準的な初期治療では十分な効果が得られない可能性が高いからです。
そのため私たちの研究室では、実際の患者検体からさまざまな生物学的情報を収集し、治療に反応する腫瘍と持続する腫瘍を分ける分子的特徴(シグネチャー)を特定することに取り組んでいます。将来的には、これらの分子シグネチャーを用いることで、医師が治療の効果を予測し、適切なタイミングで治療方針を決定できるようになることを目指しています。
なぜ画像技術ではなく、分子アッセイに注目するのですか?
PETスキャンや代謝イメージングは非常に有用ですが、技術的・運用上の制約もあり、それらを分子アッセイで改善できると考えています。
実際のところ、画像診断は高額で患者への負担も大きいため、長期的な研究に必要な縦断的データの収集が難しく、疾患の長期モニタリングにおいても障壁となり得ます。
超高感度なctDNA検出技術について
最近の研究で、Personalis社の研究チームは、ctDNA(循環腫瘍DNA)の検出に特化したアプローチを開発し、わずか3.45 PPM(百万分の3.45)という極めて低い検出限界(LOD)を実現しました。詳しくは以下の論文をご覧ください:
Analytical validation of NeXT Personal®, an ultra-sensitive personalized circulating tumor DNA assay. Oncotarget, 2024. doi: 10.18632/oncotarget.28565
技術的な観点から見ると、PETスキャンなどの画像診断では、感度や特異度が不十分な場合があります。そのため、疾患の兆候や残存病変の発見・対応に時間がかかり、結果として患者ケアが遅れることがあります。また、後ろ向き研究で用いられる「寛解」などの診断結果が、生物学的事実を正確に反映しているのか、それとも検出技術の限界による見かけの結果なのか判断がつかないという問題もあります。
この点、分子診断の大きな利点の一つは、PETスキャンや代謝画像と比較して高い特異性を持っていることです。より正確な治療効果の評価が可能になれば、臨床判断の質も向上します。さらに、分子検査が画像検査よりもコスト面で有利になる可能性もあり、特に血液ベースの検査であれば、長期モニタリングのために繰り返し検体を採取することも容易になります。
理想的な分子アッセイとは?
私たちが本当に求めているのは、侵襲性が低く、頻繁にサンプリングできる高感度な分子アッセイです。私が関わっている白血病の研究では、病態の進行が非常に速く、骨髄生検の頻度にも限界があります。現時点でも、clonoSEQなどの分子ツールを活用して疾患の特性を把握していますが、治療に伴う新たな遺伝子変異の出現を捉えられるような、より広範な生物学的情報の取得が可能になれば、さらに大きなメリットがあります。
こうした情報は、より多くの侵襲的な骨髄生検を実施することで得られるものではありません。必要なのは、疾患の特性を捉え、かつ治療反応を適切なタイミングで追跡できる、感度・特異性ともに優れた血液や血漿ベースの検査なのです。これは、白血病やリンパ腫領域において現在も満たされていないニーズであり、私たちはcfDNA(セルフリーDNA)を用いた研究を通じて、この課題を解決することを目指しています。
cfDNAから得られる情報とは?
cfDNAは非常に興味深いバイオマーカーです。検出自体は難しいものの、十分な感度を持つアッセイを使えば、疾患の生物学的な側面を深く理解するための“窓”となります。cfDNAをシーケンシングすることで、がんの状態をより詳細に把握することができ、がんのタイプ、初期治療への反応性、新たな遺伝子変異の有無など、臨床上重要な情報が得られます。
私たちの研究室を含め、多くのグループがcfDNAを用いた腫瘍反応(病勢)モニタリングの有用性を検証しています。次世代シーケンシング(NGS)を用いて、治療の初期段階(最初の1~3サイクル)でcfDNAを解析し、分子的な治療反応を評価するとともに、寛解後にも病変が残存するリスクを予測することを目指しています。
ウェビナー|Preparing For ctDNA
循環腫瘍DNA(ctDNA)の検出には、事前の準備がすべてといっても過言ではありません。本ウェビナーでは、ピーター・マッカラムがんセンターがんゲノミクス・トランスレーショナル研究センターのStephen Wong博士が、Twist cfDNAライブラリー調製キットを用いたターゲットキャプチャによるセルフリーDNAからの変異検出について紹介しています。
cfDNAは、画像診断では検出が難しい微小残存病変(MRD)や病状の進行を、より早期かつ長期にわたって予測・検出できる可能性を秘めています。これまでの多くの研究では、初回治療後にcfDNAでMRDが検出された患者は、再発リスクが高いことが示唆されています。このような患者に対しては、骨髄移植を目指した集中的かつ統合的な治療を早期に行うことが重要です。
特にリンパ腫領域では、このような集中的治療が必要な患者を正確に特定できることが極めて価値あるものです。というのも、リンパ腫は高齢の患者に多く、他の併存疾病を抱えていることも少なくないため、治療による毒性を最小限に抑えることが非常に重要になります。cfDNAから残存病変や特定の分子シグネチャーを検出することで、より強力な治療法の使用を正当化する根拠になる一方で、cfDNAに変化が見られなければ、過剰な治療を回避する判断材料としても役立ちます。最終的には、臨床医が重要な判断を下す際に、最も信頼できるデータを提供することが鍵となるのです。
cfDNA検出へのアプローチ
私たちは主にカスタムパネルを使用しています。cfDNA検出にはさまざまな方法がありますが、私たちの分子診断プログラムの基本的な考え方は、「すべてを完璧にこなせる単一のアッセイやプラットフォームは存在しない」ということです。そのため、目的に応じた最適なアッセイ(fit-for-purpose assay)を設計することが非常に重要です。というのも、cfDNAから得たい情報は多岐にわたるからです。ある時は疾患の特徴を知るために、遺伝的・エピジェネティックなマーカーを調べる必要があり、また別の時には、複数のバイオマーカーを統合して免疫系に関する情報まで抽出する必要があります。つまり、cfDNAを用いた検査には、多層的な生物学的情報の解明と臨床応用の橋渡しを同時に進める柔軟性と精度が求められているのです。
🧬 Twist カスタムパネルとホワイトグローブサービス
TwistのカスタムNGSパネルは、各研究室のニーズに合わせて設計されており、高解像度かつ深いカバレッジにより、効率的かつ高感度なデータ収集を可能にします。
Twistのプローブは、挿入/欠失変異、融合遺伝子、マイクロサテライト不安定性(MSI)などの臨床的に重要なゲノム変異をターゲットにしており、特異性を損なう繰り返し配列の影響を避けるよう設計されています。
Twistでは、設計から製造までクライアントと密に連携し、オーダーメイドのパネルを最適化するために全力で取り組みます。この協働プロセスにより、100本〜100万本以上のプローブ数に対応した多様なパネル設計、標的領域、タイル設計、GC含量の調整など、柔軟な開発が可能です。
私たちは、生物学的・臨床的な問いに適したアッセイ設計を常に意識しており、その場に最も適したものを作ることを目標としています。カスタムパネルによって新たな有望な知見が得られた場合は、それをより大規模な研究に展開することも視野に入れています。
Twistが私たちの研究をどう支えてくれているか
私がTwistと関わり始めたのは2019年で、過去5年間にわたってさまざまなプロジェクトで協力してきました。私たちは数多くのターゲットパネルを使用しており、その中で特に重視しているのが一貫したカバレッジ性能です。
単なる「変異がある/ない」の検出だけではなく、定量的なバイオマーカーを多数扱い、それを統合的に分子レベルでの腫瘍負荷評価に活用しているため、ターゲットアフィニティのばらつきは避けたい要素です。その点、Twistのターゲット濃縮用ベイトは、非常に安定したカバレッジを提供してくれており、強く信頼しています。
また、Twistのパネル設計チームとのやり取りも非常に良好です。これまでに複数の設計担当者と協働してきましたが、どのケースでも非常にスムーズでした。通常、カスタムパネルの設計では、予期しない性能問題が生じた場合、大幅な再設計が必要になることがあります。特に新しい領域や手法を取り入れる際は、非特異的なベイトが生じ、オフターゲットリードが増えるリスクがあります。
しかし、Twistの内部ツールとノウハウのおかげで、大幅な再設計はほとんど発生していません。私たちのラボは、Twistとの長期的な関係性から多くの恩恵を受けており、設計者がこちらのニーズや目的をすぐに理解してくれるため、非常に効率よく開発が進められています。
だからこそ、私たちはTwistを継続的に使用しています。化学面での安定した性能と、設計チームとの協力体制、その両方が非常に貴重だと感じています。
今後の展望について
私たちは常に「血漿ベースのアナライトから、さらに何が得られるか?」を模索しています。がんの中には、明確なドライバー変異を持たない、エピジェネティックな要因に依存する疾患状態もあります。この領域で、私たちはいくつかのパイロット研究を開始しており、まだ未知の分野が多い中で取り組めるのはとても刺激的です。
独自の患者コホートを対象に、腫瘍細胞やcfDNAのさまざまな特徴を調べられるツールを活用し、従来のcfDNAアッセイと統合可能な可能性を探っていきたいと考えています。
👉 Twistの詳細と、がん研究を支える取り組みについてはこちら >>
Twist製品は研究用に限定されています。病気の診断・予防・治療を目的とした使用はできません。また、本製品の使用結果は特定の施設で得られたものであり、すべての施設で同等の性能を保証するものではありません。
いかがでしたか?(リンク先のページの最下部から投票いただけます)